2025.05.15
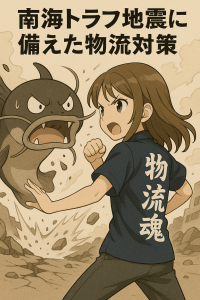
日本の物流網は、地震や津波などの自然災害による影響を常に意識しながら整備されています。その中でも、特に南海トラフ地震が発生した場合には、物流チェーンに甚大な被害が及ぶ恐れがあります。本記事では、南海トラフ地震のリスクと、それに対する物流業界の備え・対策を解説します。
南海トラフ地震とは、紀伊半島沖から九州南岸にかけた海底の深い溝(トラフ)で発生する大規模地震を指します。過去には1707年の宝永地震(M8.6)、1946年の昭和南海地震(M8.0)、1944年の東南海地震(M7.9)などが起こっており、今後30年以内にM8クラスの地震が高い確率で発生すると予測されています。
主な予測被害
津波浸水:津波による港湾施設や倉庫の浸水・流失
道路寸断:沿岸部および山間部の国道・高速道路の損壊
鉄道不通:鉄道インフラの崩壊によりコンテナ貨物輸送が停滞
これらの被害は、サプライチェーンを構成する企業の生産・販売活動を一時的に停止に追い込みます。
南海トラフ沿岸には、名古屋港、神戸港、大阪港、清水港など日本の主要港湾が集中しています。津波浸水や岸壁の損壊により、コンテナターミナルや倉庫が使用不能になる恐れがあります。これにより、輸出入貨物が滞留し、荷主や製造業への納期遅延が発生します。
被災地域では道路が寸断され、トラック輸送が迂回や代替ルートの利用を余儀なくされます。さらに、鉄道コンテナ輸送(JR貨物、私鉄コキ輸送など)も長期にわたり停止し、物流コストの上昇を招きます。
沿岸部や断層帯近傍に位置する物流センターは、建屋の損壊や棚崩れ、庫内在庫の被害が予想されます。在庫のロスは企業収益を直撃するとともに、被災地以外への供給減を引き起こします。
多くの物流企業では、BCP(Business Continuity Plan)を策定し、災害発生時の初動対応や復旧手順を明確化しています。具体的には、
緊急連絡網の整備:社員・協力会社間の安否確認と情報共有
代替拠点の確保:被災時に稼働できる代替倉庫の契約
輸送キャパシティの分散化:複数の輸送ルート・モードの整備
物流企業は国や自治体が推進する道路・港湾の耐震強化事業に参加し、荷役機器や倉庫の免震・制震対策を進めています。また、ドローンや自動運転トラックなど先端技術を活用した「ラストワンマイル」物流の実証実験も活発化しています。
AIやIoTセンサーを用いたリアルタイム在庫管理システムを導入し、被災時の在庫変動を即座に把握できる環境を整備。さらに、クラウド型プラットフォームで荷主と共有することで、需給変動への即応性を高めています。
南海トラフ地震のような大規模災害では、一社だけの対策では限界があります。
自治体との協定:避難場所としての倉庫提供やガソリン供給支援
共同備蓄センター:複数企業での共同在庫センター運営
情報共有プラットフォーム:災害時の道路・港湾状況をリアルタイムで共有
これらの取り組みにより、被災地の物流網を早期に復旧し、生活物資や医療物資の迅速な輸送が可能になります。
南海トラフ地震は、日本の物流にとって最大級のリスクです。しかし、BCP策定やインフラ強靱化、先端技術活用、地域連携といった多層的な対策により、被害を最小限に抑え、復旧を加速させることができます。物流企業は日頃から対策を磨くとともに、荷主や自治体と協力し、サプライチェーン全体の強靱化を目指しましょう。
大阪で運送の仕事はニュートラルにお任せください!見積もりのご依頼をお待ちしております。

定期便・イベント輸送・当日便・夜間搬入・チャーター便・貸切便・混載便等様々な配送に対応いたします。繁忙期の為他社に断られた・急に荷物を届けないといけない等にも柔軟に対応いたします。配送のことならどんな事でもお気軽にご相談下さい。

配送エリアやお荷物の量に応じて料金が異なります。こちらから料金表をご確認下さい。尚、定期でのご契約や料金表に記載のない特殊な配送は別途お見積りいたしますのでお問合せ下さい。またお急ぎの場合はお電話での対応も可能です。

弊社に配送をご依頼いただいたお客様の声をご覧いただけます。実際に依頼いただいたお客様の生の声をご覧いただくと、弊社の物流に対しての考え方や様々な配送ケースを参考にしていただけると思います。